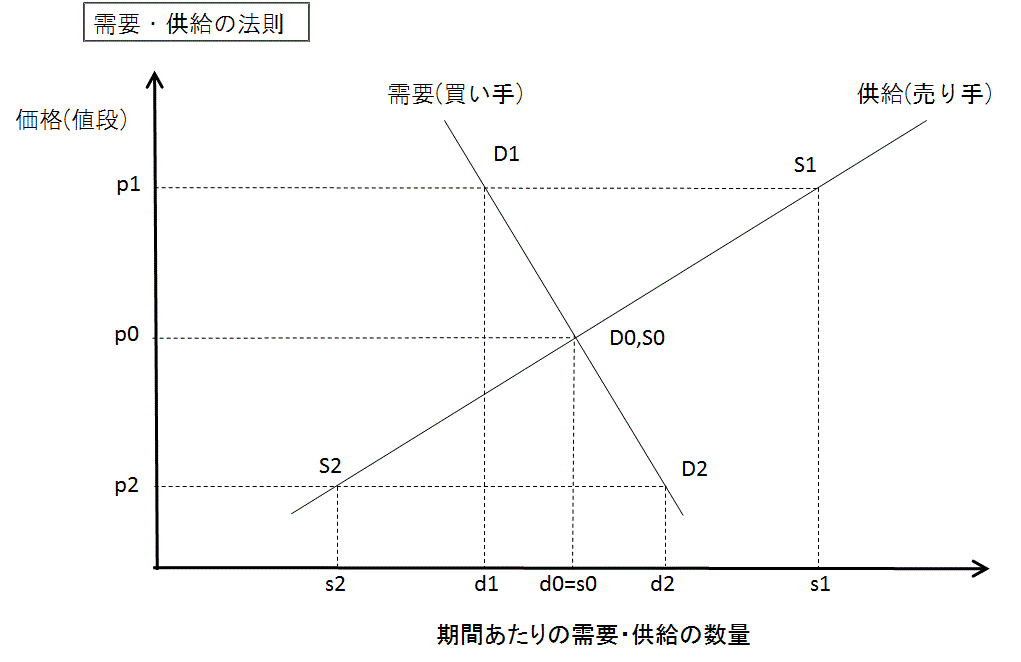さていよいよ『一般理論』です。
まずはじめの『序文』の所には、この本の読者として想定しているのは経済学者だ、と宣言しています。古典派の経済学者に対して、『これから古典派の経済学は間違いだということを説明しますよ』と宣言しているわけです。
次の『第一章 一般理論』の所では一般理論の『一般』という言葉を使ったわけを説明しています。すなわち古典派の経済学は一般的には現実の世界では成立しないので、その代わりに現実の世界で一般的に成立する経済学をこれから説明します、と宣言します。
さらに、古典派の経済学は非現実的なものなので、それを現実に適用すると悲惨なことになりますよと言って、古典派の経済学者を挑発しています。
それでいよいよ『第二章 古典派の経済学の公準』という所から具体的な議論が始まります。
ケインズの経済学の基本的なテーマの一つは、大恐慌のあとの大量失業の問題ですから、これを踏まえ、この章では労働の需要と供給について古典派はどのように考えているのか、その考えはどのように間違っているのか、という議論をします。これは第三章以下でケインズ自身の労働の需要の理論をする前置きとなっています。
『失業』といっても自発的失業、すなわち『仕事口はあるんだけれど仕事したくない』というような失業は対象とはしません。自分で勝手に失業してるんだから、というような意味です。で、問題にするのは『非自発的失業』、すなわち働きたいのに仕事口がない、という失業がどうして起こるのか、という問題です。
1929年の大恐慌で世界的に失業者が溢れました。これは誰の目にも明らかだったんですが、古典派はこれをどう見たかというと、『労働』というのも他の普通の商品と同じく売り買いされるものだと考え、ここでも需要・供給の法則が成り立っていると考えると、自動的に値段(この場合は労賃)と、売買される数量(ここでは雇用される労働者数)が決まり、そこでは需要と供給が一致しているんだから、失業(すなわち供給過剰・需要不足)は発生するはずがない。にもかかわらず失業者がいるということはマーケットが間違っている、と考えるわけです。
労働の需要曲線と供給曲線を書けば、その交わった所で値段(労賃)が決まり、需要と供給がマッチする。需要不足が発生するというのは、値段が高止まりしていて本来的に下がるはずなのに下がらない、誰かが下がるのに抵抗しているからだということで、労働者が賃下げに反対して抵抗しているから賃金が下がらず、そのため需要不足で失業者が発生してしまうんだ、という理屈です。
この理屈にケインズは反論するんですが、その前に古典派の経済学による労働の需要曲線・供給曲線がどのように作られるかを説明しています。この需要曲線・供給曲線の作り方のことを、ケインズは『公準』と呼んでいるんですが、それは次のようなものです。
<第一の公準>(需要曲線の作り方)
賃金は労働の限界生産物に等しい。
<第二の公準>(供給曲線の作り方)
労働雇用量が与えられた時、その賃金の効用はその雇用量の限界不効用に等しい。
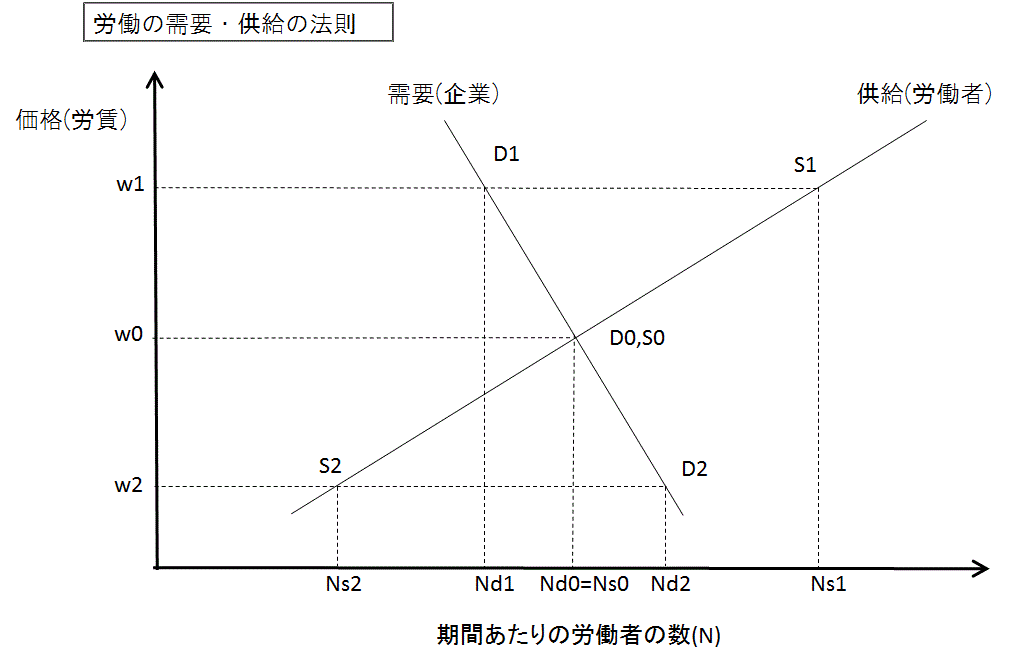
まず第一の公準は需要の方ですから、労働の買い手、すなわち『雇い主がどのように考えて労働を買う(労働者を雇う)か』ということです。
労賃がwの時、企業がN人雇うというのは、N人までは雇う人数が多ければ多いほど儲かるけれど、N+1人目を雇うとかえって儲けが減ってしまうということです。N+1人目を雇うと、労賃が1人分wだけ増えます。N+1人目を雇うことによって生産量がΔqだけ増えて、売り上げがp・Δqだけ増えるとします。その生産のために労賃以外に一個あたりcだけ費用が増えるとすると、儲けの増え方はp・Δq-c・Δq-wとなります。
これがプラスのうちはN人雇うよりN+1人雇う方が儲かるので、Nは増やす方が良いし、これがマイナスになるとNは増やさない方が良い。すなわちそれぞれのwに対してp・Δq-c・Δq=wとなる所、すなわち(p-c)・Δq=wとなる所のNをつないでできるのが、需要曲線になるということです。
この(p-c)・Δqというのは、N+1人目を雇った時の生産量の増加分Δqに対する、(労賃を除いた)儲けの増分です。これを経済学では労働の限界生産物、すなわち労働者を一人増やした時の生産高(売上から費用分のcを引いた分)の増加分だ、というように表現します。そこでw=(p-c)・Δqを言葉で言うと、『労賃は労働の限界生産物に等しい』ということになるわけです。
次に第二の公準は供給曲線ですから、労働の売り手すなわち『労働者がどのように考えて雇われるか』の問題になります。
労働者がN人働いていて、さらにもう一人N+1人目が働くかどうは、そのN+1人目の人にとって、貰う賃金の効用(満足感)が働くことによるマイナスの効用、すなわち『疲れる』とか『時間が自由にならない』とかの不満感を上回るかどうかで決まるということです。
ここで労働者は皆同じだけの、たとえば週5日・1日7時間働くといった、一定の期間(週)あたり一定の時間(35時間)働くことを前提としています。
労賃wが決まった時、その労賃で労働者が働くかどうかは、それぞれの労働者ごとに違います。それぞれの労賃wごとに、それぞれの人ごとに労賃の効用(満足感)と働くことによる不効用(不満感)を比較し、『働く』という結論の出る人数を数えたものが労働の供給曲線となるという仕組みです。
ここで労賃がwの時、N人目までは労賃の効用が労働の不効用を上回っているけれど、N+1人目を雇った時の、雇われた人全体の労働の不効用の合計の増加分、すなわちN+1人目の人の労働の不効用が賃金と等しくなるということです。一人分の労働者の限界不効用というのを、一人分の労働の限界不効用と言っています。
これで労働の需要曲線・供給曲線ができたので、この曲線の交点を求め、その交わった所の労賃と労働者数で実際に取引される(即ち労働者の雇用が行われる)ということになります。
ケインズによればこれが古典派が考える労働者の雇用の決まり方だ、ということです。
この第二章の話、もう少し続きます。